ポケモンを英語で語ろう!みずタイプ編|海外ファンと盛り上がるためのフレーズ集


「海外の友達とポケモンの話をしてみたい!」と思ったことはありませんか?
ポケモンは日本発の大人気ゲーム・アニメですが、今では世界中で愛されるグローバルコンテンツです。
実際、海外のアニメイベントやゲームフェスでは、ポケモンのコスプレやグッズが必ずと言っていいほど見られます。
ただし、注意したいのがポケモンの名前は日本語版と英語版で大きく違うことが多いという点。
例えば「ゼニガメ」は英語では Squirtle。日本語に慣れている私たちからすると、「誰それ?」となりがちです。
今回は、その中でも御三家や伝説が多く、特に人気の高いみずタイプ(Water-type)にフォーカス!
代表的なみずポケモンの英語名リストをまとめました。
この記事を読めば、海外のポケモンファンとの交流がぐっと楽しくなりますよ。
関連記事:ポケモンを英語で語ろう!くさタイプ編|海外ファンと盛り上がるためのフレーズ集
目次
みずタイプ代表ポケモン 英語と日本語のリスト


特に人気のあるみずタイプのポケモンをピックアップしました!
日本名・英語名・由来を合わせてチェックしましょう。
英語名の由来も、日本語名と同じく「言葉遊び」で名付けられていることが多いですよ。
カントー地方のみずタイプポケモン(第1世代)
- Squirtle(ゼニガメ):Squirt(水を吹き出す)+turtle(カメ)
- Wartortle(カメール):Water(水)+turtle
- Blastoise(カメックス):Blast(水流・爆発)+tortoise(カメ)
- Psyduck(コダック):Psychic(超能力)+duck(アヒル)
- Golduck(ゴルダック):Gold(金色)+duck
- Poliwag(ニョロモ):Polliwog(おたまじゃくし)由来
- Poliwhirl(ニョロゾ):Polliwog+whirl(渦巻き)
- Poliwrath(ニョロボン):Polliwog+wrath(怒り)
- Magikarp(コイキング):Magic(魔法)+carp(コイ)
- Gyarados(ギャラドス):日本語版と共通で、怒涛・ギリシャ語の“怒り”に由来する説がある
- Lapras(ラプラス):フランスの数学者ラプラス、または“波がやさしく打つ”の意味を持つ英語 lap 由来とも言われる
ジョウト地方のみずタイプポケモン(第2世代)
- Totodile(ワニノコ):Tot(子ども)+crocodile(ワニ)
- Croconaw(アリゲイツ):Crocodile+gnaw(かじる)
- Feraligatr(オーダイル):Ferocious(凶暴な)+alligator
- Marill(マリル):Marine(水)+rill(小川)
- Azumarill(マリルリ):Azure(青)+marill
- Suicune(スイクン):水(sui)+君主の君(kun)※中国の伝説上の神獣「瑞獣(スイキン)」に由来するという説も。
ホウエン地方のみずタイプポケモン(第3世代)
- Mudkip(ミズゴロウ):Mud(泥)+skip(跳ねる)
- Marshtomp(ヌマクロー):Marsh(湿地)+stomp(踏む)
- Swampert(ラグラージ):Swamp(沼)+expert(達人)
- Lotad(ハスボー):Lotus(ハス)+tadpole(おたまじゃくし)
- Lombre(ハスブレロ):Lotus+sombrero(帽子)
- Ludicolo(ルンパッパ):Ludicrous(陽気な)+colo(踊る響き)
- Kyogre(カイオーガ):Kai(海)+ogre(鬼)
シンオウ地方のみずタイプポケモン(第4世代)
- Piplup(ポッチャマ):Pip(小さな鳴き声)+plop(水音)
- Prinplup(ポッタイシ):Prince(王子)+plump(ふくよか)
- Empoleon(エンペルト):Emperor(皇帝)+Napoleon
- Buizel(ブイゼル):Buoy(浮く)+weasel(イタチ)
- Floatzel(フローゼル):Float(浮く)+weasel
- Manaphy(マナフィ):Mana(生命力)+fi(フィーリング)
- Phione(フィオネ):フィジー諸島やsea anemone由来とも言われる
イッシュ地方のみずタイプポケモン(第5世代)
- Oshawott(ミジュマル):Otter(カワウソ)+wash(水で洗う)
- Dewott(フタチマル):Dew(水滴)+otter
- Samurott(ダイケンキ):Samurai+otter
- Panpour(ヒヤップ):Pan(猿の属名)+pour(水を注ぐ)
- Simipour(ヒヤッキー):Simian(猿)+pour
- Alomomola(ママンボウ):Aloha(挨拶・愛)+mola(マンボウ)
カロス地方のみずタイプポケモン(第6世代)
- Froakie(ケロマツ):Frog(カエル)+rookie(新米)
- Frogadier(ゲコガシラ):Frog+brigadier(軍人)
- Greninja(ゲッコウガ):Grenade(手りゅう弾)+ninja
- Clauncher(ウデッポウ):Claw(ハサミ)+launcher(発射する)
- Clawitzer(ブロスター):Claw+howitzer(大砲)
アローラ地方のみずタイプポケモン(第7世代)
- Popplio(アシマリ):Pup(子)+lio(海獣の響き)
- Brionne(オシャマリ):Brio(活発)+anne(女性名)
- Primarina(アシレーヌ):Prima donna(歌姫)+marine(海の)
- Wishiwashi(ヨワシ):Wishy-washy(弱々しい)+wash(洗う)
ガラル地方のみずタイプポケモン(第8世代)
- Sobble(メッソン):Sob(すすり泣く)+bubble(泡)
- Drizzile(ジメレオン):Drizzle(小雨)+reptile(爬虫類)
- Inteleon(インテレオン):Intelligent+chameleon
- Arrokuda(サシカマス):Arrow(矢)+barracuda(カマス)
- Barraskewda(カマスジョー):Barracuda+askew(斜め)
パルデア地方のみずタイプポケモン(第9世代)
- Quaxly(クワッス):Quack(アヒルの鳴き声)+splashly
- Quaxwell(ウェルカモ):Quack+well(上達)
- Quaquaval(ウェーニバル):Quack+carnival(カーニバル)
- Veluza(ミガルーサ):“Velu”(鋭い)+barracuda(カマスの一種) 由来
- Palafin(イルカマン):Paladin(聖騎士)+fin(ひれ)
日本名と英語名が全く違う場合があるので、名前の由来と一緒に覚えておくと連想しやすいですね。
まとめ


「ポケモン 英語 みずタイプ」という、好きな趣味のテーマで英語を学べば、好きなポケモンを通して楽しく英語を身につけられます。
また英語でのポケモンの名前を知っておくと、海外ファンとのポケモン会話がぐっとスムーズになりますよ。
この記事でお伝えした内容が、あなたの英語学習をより充実したものにできれば幸いです。
本記事のポケモンの名前由来リストは、PokémonDB、Bulbapedia、 Lingopie、ならびに公式サイトPokémon.comの記事を参考に作成しました。
また、英語学習方法にお悩みの方や英会話スクールで英語力が思っていたより伸びなかったという人におすすめなのが、英語コーチングです。
英語コーチングのTORAIZでは、あらゆる英語学習の中から、あなたにとってベストな英語学習をカスタムして、飛躍的な英語力の向上を図ることが出来ます。
英語コーチングとは、ただ英語を教えるだけでなく科学的根拠に基づいて効果的な勉強法を無理なく継続させる事に注力した英会話サービスです。
TORAIZは、そんなコーチング英会話の中でも継続率が91%以上!
英語力だけでなくコーチングの技術も洗練されたコンサルタントが、あなただけのために作られたスケジュールを管理しながら、無理なく挫折しない方法であなたをサポートします。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
短期で英語を話せるようになりたい方に
おすすめのスクールは「トライズ」
トライズは、日本人コンサルタントとネイティブコーチが専属でサポートしてくれる、英語コーチングスクール。レッスンは週3回確保される上に受け放題。マンツーマンの面談やメールで日々サポートも受けられて、他のスクールとは一線を画す本格的なプログラムになっています。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
受講生のインタビューもご紹介します。


トライズでの1年は、
一生につながる1年だったと思います。
プロキャディ杉澤伸章さん
インタビュー
Versant 29 → 40
目標:海外選手に英語でインタビューする。達 成
英語に関しては、1年前の僕と今の僕を比較すると、めちゃくちゃ成長しました。僕にとって情報源がものすごく増えたんです。 ゴルフ専門チャンネルで解説をしているのですが、そのときに現地の音声や解説者の声など英語でしゃべってくる音声が全て聞こえてきます。
それはテレビでは放送されていないのですが、映像だけでは入ってこない情報が耳から入ってくるので、それを聞きながらしゃべっています。 現地のリポーターや解説者は一番リアルな情報なので、それが耳に入ってくることによって、例えば解説でも「今、現地ではこういうことを言っていますね」ということが、スッと言えるようになりました。


















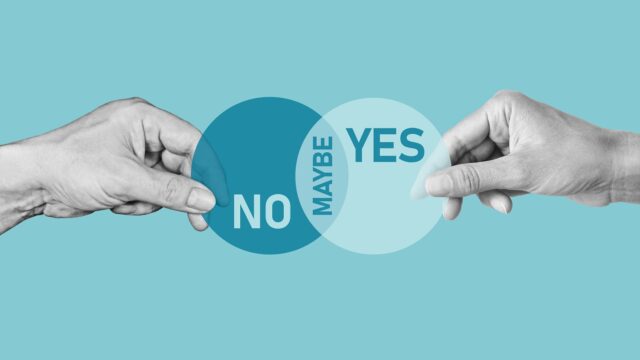




![TORAIZ[トライズ]](https://toraiz.jp/english-times/assets/img/banner/toraiz_main.png)