【TOEIC直前一夜漬け】禁断の駆け込みテクニック7選
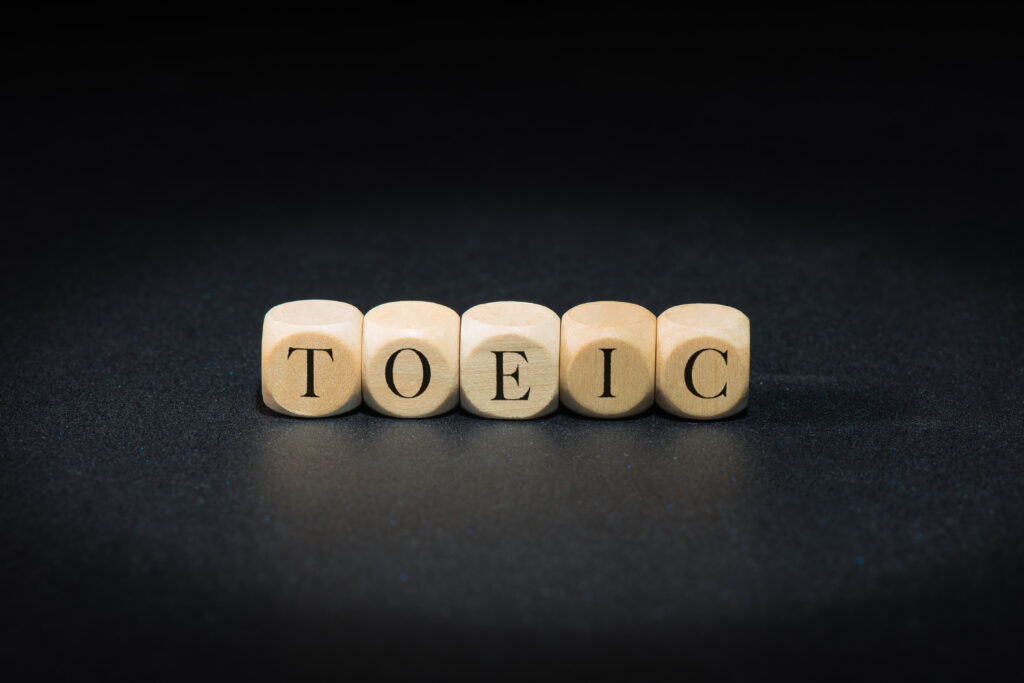
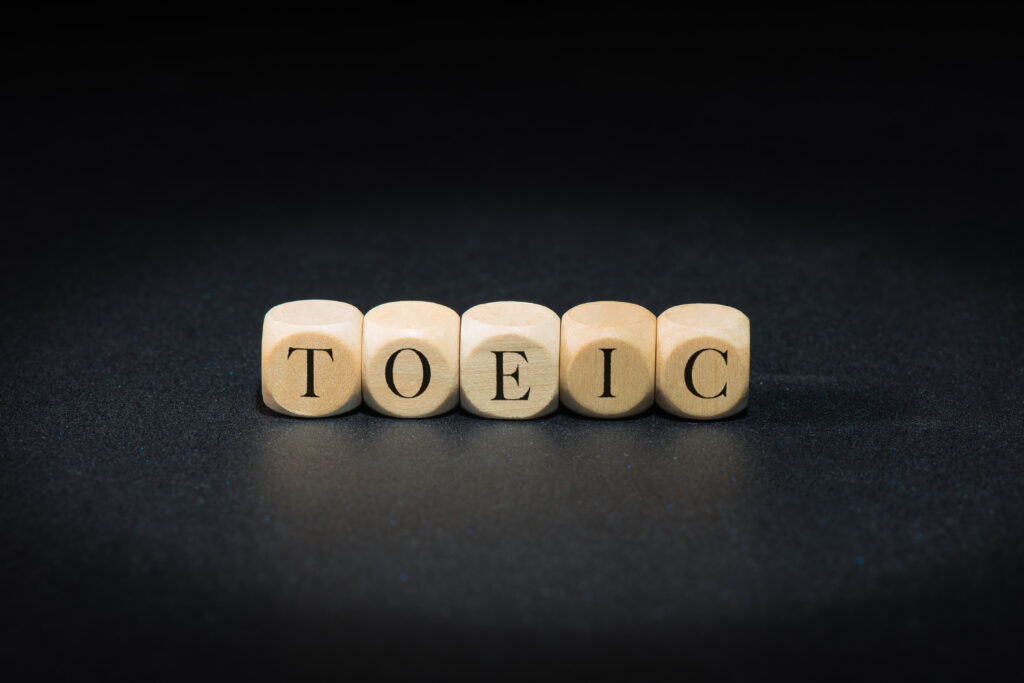
「まずい、TOEICの試験が迫っている…」「忙しくて、まったく勉強できていない…」
今、この記事を読んでいるあなたは、そんな絶望的な状況にいるかもしれません。
この記事では、直前に知るだけでスコアが数十点上がる、禁断のテクニックを7つまとめました。
この禁断のテクニックを知っているか知らないかで、あなたのスコアは大きく変わるはずです。
関連記事:TOEIC 1週間前の悪あがき!スコアを最大化する7日間の勉強法ロードマップ
目次
TOEIC直前に知るだけでスコアが上がるテクニック


TOEIC直前に知るだけでスコアが上がるテクニックは以下の7つです。
- 【共通】全問解こうとしない
- 【パート2】文頭の疑問詞に全神経を集中させる
- 【パート2】「Yes/No」で答えられない質問の選択肢は即消去する
- 【パート2】「I don’t know(分からない)」系の回答は正解率が高い
- 【パート3・4】先読みがとにかく大切
- 【パート5】選択肢から問題形式を判断する
- 【パート7】件名や差出人など細かいところもチェックする
それぞれ詳しく解説します。
【共通】全問解こうとしない
まず、試験全体を通して最も重要な心構えは「全問を完璧に解こうとしない」ということです。
特にリーディングセクションは、高得点取得者でない限り、最後まで解き終わらないことが普通です。
「全部解かなければ」という焦りは、集中力を奪い、簡単な問題でのケアレスミスを誘発します。
分からない問題、時間がかかりそうな問題に遭遇したら、深く考え込まずに潔くマークし、次の問題に進む勇気を持ちましょう。
15秒考えて分からなければ、勘でどれかをマークすると決めておくのです。
この「捨てる勇気」を持つだけで、時間配分が劇的に改善され、取れるはずの問題を確実に拾うことができ、結果的にスコアは上がります。完璧主義を捨てることが、高得点への第一歩です。
【パート2】文頭の疑問詞に全神経を集中させる
リスニングのPart 2は、短い質問に対して最も適切な応答を選ぶ問題です。対策をしていない人にとっては、質問文全体を聞き取ろうとして、結局何も分からなかった、となりがちです。
ここでの鉄則は、「最初の1単語(疑問詞)に全神経を集中させる」ことです。質問文が When で始まれば「時」、Where なら「場所」、Who なら「人」に関する選択肢が正解になります。
たとえ文の後半が聞き取れなくても、この最初の単語さえ聞き取れれば、正解の選択肢はかなり絞られます。
例えば、When is the meeting? の meeting が聞き取れなくても、When が聞こえれば At 2 p.m. のような「時」を表す選択肢を選べばよいのです。Part 2は、文頭が命だと心得ましょう。
【パート2】「Yes/No」で答えられない質問の選択肢は即消去する
TOEICのPart 2では、疑問詞(Why, When, Where, Who, How, What)で始まる質問に対して、「Yes」や「No」で答える選択肢は100%不正解です。
例えば、Why was the flight delayed?(なぜフライトは遅れたのですか?)という質問に対して、Yes, it was. と答えるのは文法的におかしいですよね。
リスニング中に選択肢が Yes や No で始まったら、それが疑問詞の質問に対する答えである場合、即座に不正解として消去できます。
これにより、正解の確率を50%や100%に高めることができる問題が少なからず存在します。これは知っているだけで使える、非常に有効なテクニックです。
【パート2】「I don’t know(分からない)」系の回答は正解率が高い
Part 2の質問に対して、必ずしも直接的な答えが返ってくるとは限りません。
むしろ、現実の会話のように、はぐらかしたり、分からないと答えたりする選択肢が正解になるパターンが非常に多いのです。
“I have no idea.” (分かりません)、“It hasn’t been decided yet.” (まだ決まっていません)、“Let me check.” (確認します)、“Ask someone else.” (他の人に聞いてください) といった、いわゆる「分からない・知らない」系の回答は、正解になる確率が統計的に高いということを覚えておきましょう。
直接的な答えの選択肢で迷ったら、「逃げ」の回答をしている選択肢を積極的に疑ってみてください。これはTOEICが、より実践的な会話を想定していることの表れでもあります。
【パート3・4】先読みがとにかく大切
Part 3(会話問題)とPart 4(説明文問題)は、長めの英語を聞いて複数の質問に答える、リスニングの山場です。
ノー勉で挑むと、音声を聞き終えた頃には内容をすっかり忘れてしまい、勘でマークするしかなくなります。
これを防ぐ唯一にして最強のテクニックが「設問の先読み」です。
各パートの説明アナウンスが流れている間や、前の問題の回答が終わった後の数秒の間に、次に流れてくる音声で問われる設問(Question)に、必ず目を通してください。
「男性は何を心配していますか?」「女性は次に何をしますか?」といった設問を先に読んでおくだけで、「何を聞き取るべきか」という目的意識を持って音声を聞くことができます。
これにより、ただ漠然と英語を聞く状態から、「答えを探しながら聞く」というアクティブな状態に変わるのです。
選択肢まで読む時間がなくても、設問を読むだけでリスニングの精度は劇的に向上します。
【パート5】選択肢から問題形式を判断する
リーディングのPart 5は、短文の穴埋め問題です。時間がない中で、ここをいかに速く処理できるかが、後半のPart 7に時間を残すための鍵となります。
全文を律儀に読む前に、まず選択肢をチラッと見てください。
もし、(A) develop (B) development (C) developing (D) developed のように、同じ単語の形違いが並んでいたら、それは「品詞問題」です。
品詞問題は、文全体の意味が分からなくても、空所の前後の単語の並びだけで、文法的にどの品詞が入るかを判断できます。
例えば、空所の前が冠詞(a, the)で、後ろが名詞なら、間に入るのは形容詞、といった具合です。
このような問題は全文を読まずに、1問5秒で片付けましょう。この一手間が、貴重な時間を生み出します。
【パート7】件名や差出人など細かいところもチェックする
Part 7の長文読解問題では、多くの人が本文から読み始めますが、それは非効率です。
Eメール、チャット、広告といった様々な形式の文章が出題されますが、本文を読む前に、必ず周辺情報に目を通す癖をつけましょう。
特に、Eメール問題であれば「件名(Subject)」「差出人(From)」「受信人(To)」「日付(Date)」に、スコアアップのヒントが隠されています。
例えば、設問で「このメールの目的は何か?」と問われている場合、その答えが件名にそのまま書かれているケースは非常に多いです。
誰が誰に、いつ送ったのかを把握するだけで、文章全体の関係性や状況がスムーズに理解でき、結果として本文を読むスピードも、設問を解く精度も上がります。
細かい情報こそ、時間短縮の宝庫なのです。
まとめ
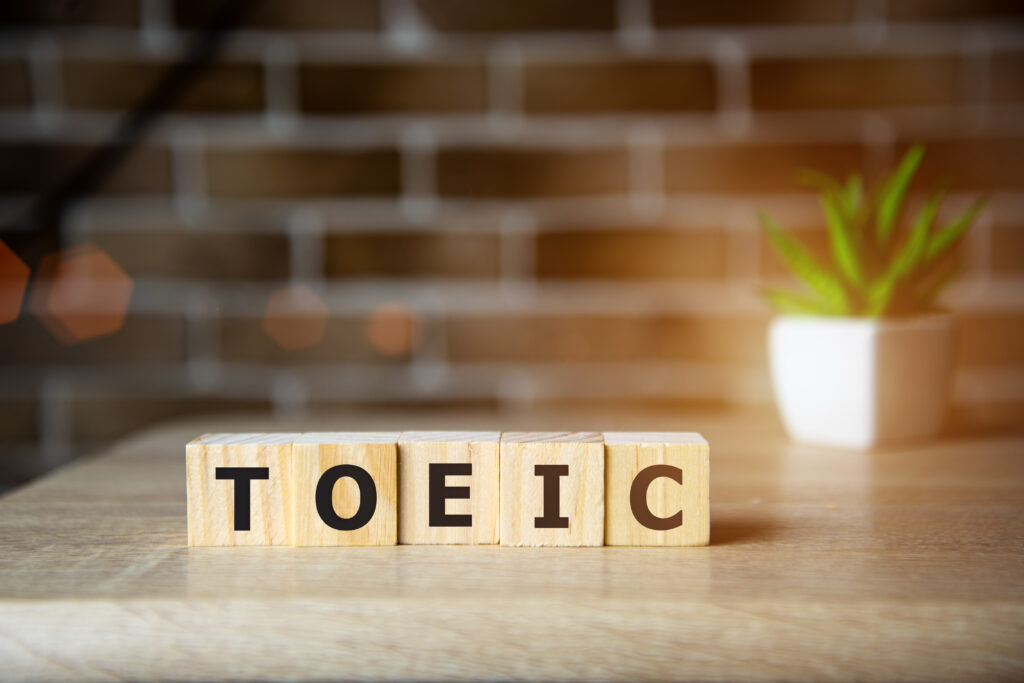
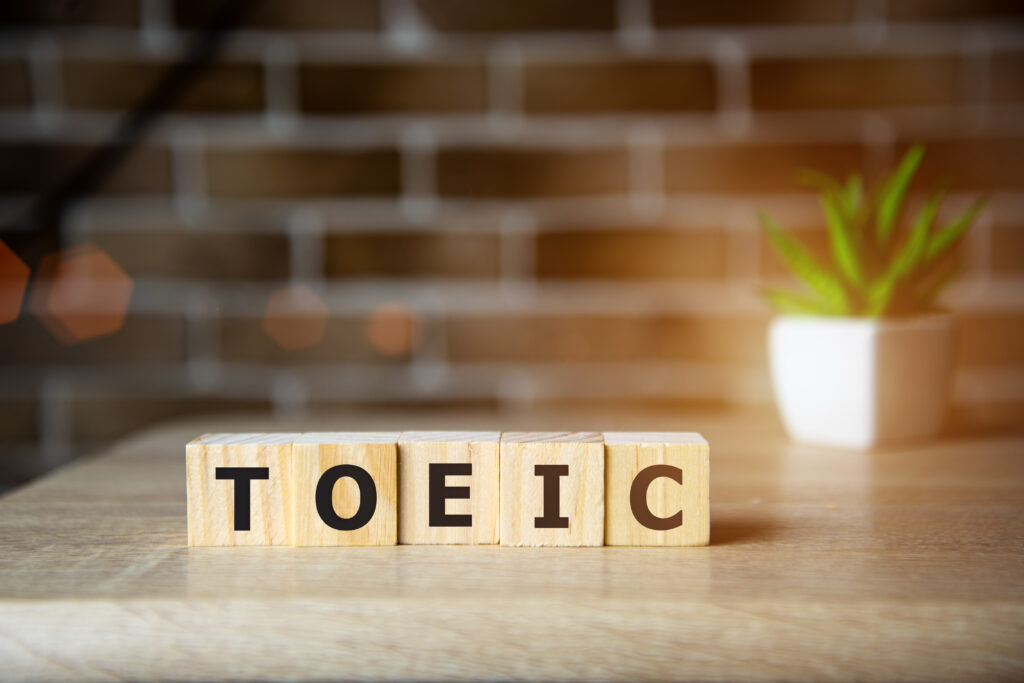
今回は、TOEICを直前に控えた「ノー勉」のあなたのために、最後の悪あがきでスコアを最大化する禁断のテクニックを解説しました。
もちろん、これらはあくまで応急処置的な「小手先の技」であり、本質的な英語力を上げるものではありません。
しかし、TOEICという試験のルールの中で、今ある実力を最大限に発揮するためには、驚くほど効果的な戦略です。
試験当日は、難しい問題に固執せず、今回紹介したテクニックを駆使して解ける問題を確実に拾っていきましょう。
そして試験が終わったら、ぜひ次回の試験に向けて、今度こそ計画的に学習を始めてみてください。
関連記事:TOEIC700点は上位30%のレベル!1ヶ月で達成するための勉強時間や必須参考書を紹介
短期で英語を話せるようになりたい方に
おすすめのスクールは「トライズ」
トライズは、日本人コンサルタントとネイティブコーチが専属でサポートしてくれる、英語コーチングスクール。レッスンは週3回確保される上に受け放題。マンツーマンの面談やメールで日々サポートも受けられて、他のスクールとは一線を画す本格的なプログラムになっています。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
受講生のインタビューもご紹介します。


トライズでの1年は、
一生につながる1年だったと思います。
プロキャディ杉澤伸章さん
インタビュー
Versant 29 → 40
目標:海外選手に英語でインタビューする。達 成
英語に関しては、1年前の僕と今の僕を比較すると、めちゃくちゃ成長しました。僕にとって情報源がものすごく増えたんです。 ゴルフ専門チャンネルで解説をしているのですが、そのときに現地の音声や解説者の声など英語でしゃべってくる音声が全て聞こえてきます。
それはテレビでは放送されていないのですが、映像だけでは入ってこない情報が耳から入ってくるので、それを聞きながらしゃべっています。 現地のリポーターや解説者は一番リアルな情報なので、それが耳に入ってくることによって、例えば解説でも「今、現地ではこういうことを言っていますね」ということが、スッと言えるようになりました。


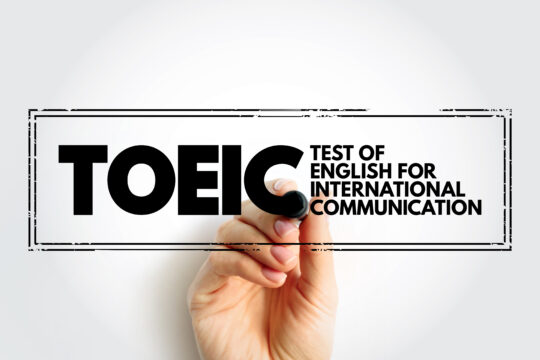

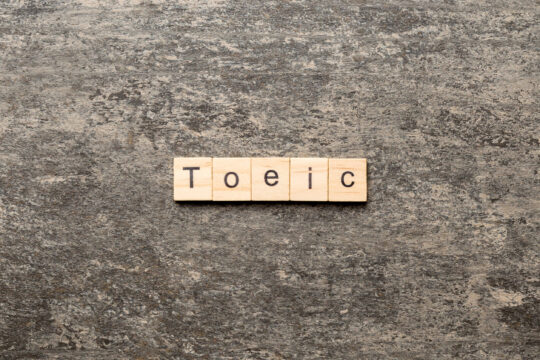
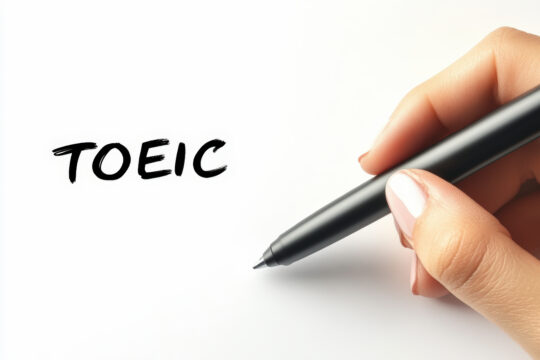
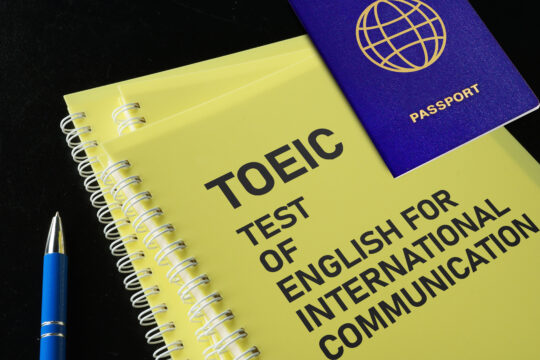
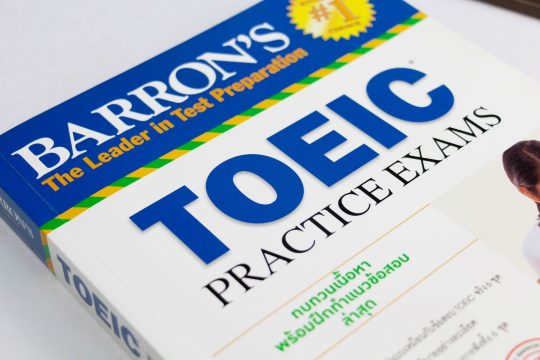





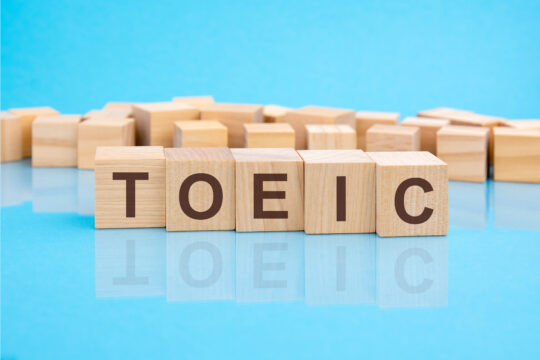
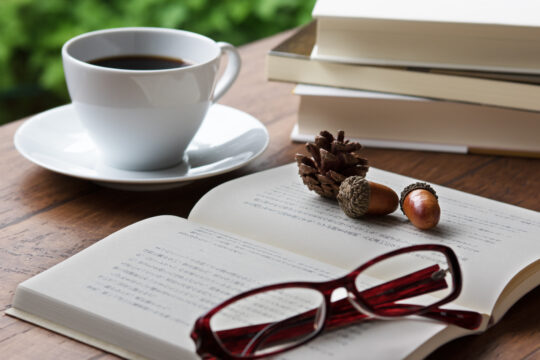
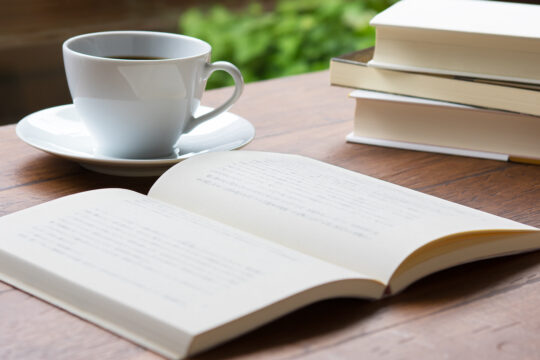







![TORAIZ[トライズ]](https://toraiz.jp/english-times/assets/img/banner/toraiz_main.png)