英語で「お疲れ様」ってなんて言う?シーン別・ネイティブの自然な言い回しも解説


「今日もお疲れ様!」
「お先に失礼します、お疲れ様でした」
↑のように、日本語では日常的に使う「お疲れ様」という表現。
相手を労ったり、お仕事の区切りなどでよく使われる言葉ですね。
そんな「お疲れ様」という言葉ですが、実は英語には、「お疲れ様」にぴったり対応するフレーズがありません。
そこでこの記事では、「英語で『お疲れ様』ってどう言えばいいの?」という疑問に、ビジネス・日常会話・チャットなどシーン別に具体的な表現例と解説を交えて丁寧にお答えします。
英語圏での文化的背景や、自然なトーンの伝え方についても触れていて、仕事や英会話レッスンですぐに役立つ知識が満載ですので、ぜひ最後まで読んでください。
目次
「お疲れ様」にぴったりな英語はない?——まずは前提を整理しよう


結論から言うと、「お疲れ様」を直接英語に翻訳できる言い方はありません。
「疲れてる」という意味での “You’re tired” はニュアンスが違いすぎますし、“Good job” や “Well done” も状況次第で不自然に感じられることもあります。
それでは、日本人がよく使う「お疲れ様」を英語で伝えるにはどうしたら良いでしょうか?
英語では「文脈に合わせた“ねぎらい”や“感謝”の言葉」を使うことで、日本語の「お疲れ様」に近い意味合いを伝えるのが一般的です。
次の項から、英語で「お疲れ様」を伝えられる、シーン別の英語を見ていきましょう。
シーン別:英語での「お疲れ様」の伝え方


ここからは、よくあるシチュエーションごとに、「お疲れ様」を伝えられる自然な英語表現を、簡単な解説付きで紹介していきます。
ビジネスシーンでの「お疲れ様でした」
職場での「お疲れ様でした」は、感謝・労い・敬意を伝える意味で使われますね。
英語では、相手との関係性に応じて使い分けるのがポイントです。
例文と解説↓
- Thank you for your hard work today.
→「今日もお疲れ様でした」という定番の丁寧表現。チーム全体にも使える万能フレーズです。 - I really appreciate your efforts on the project.
→「プロジェクトへの取り組みに感謝します」。特定の成果や業務に対して労うときに。 - Great job today!
→ もっとカジュアルに伝えたいときに。上司→部下、同僚同士にも。 - Have a good evening.
→ 相手が退勤する時の「お疲れ様でした+帰宅を気遣う」場面に最適です。
関連記事:「ありがとうございます」と丁寧に感謝を伝える英語表現23選【ビジネス・メールでも使える】
友人・同僚とのカジュアルな「おつかれ〜」
友達や仲間とのやりとりで使う「おつかれ〜」は、ねぎらいというより“あいさつ”に近い感覚で使うのではないでしょうか?
英語で「おつかれ~」を表現する時は、フレンドリーな言い方で伝えるのが自然です。
例文と解説:
- Take it easy.
→ 直訳は「無理しないでね」。帰り際の軽い一言としても使えます。 - Nice hustle today!
→ “hustle”は頑張ったニュアンス。スポーツやイベントなど体を動かした後にピッタリ。 - You did great.
→ その日の成果や頑張りに対して、フレンドリーにねぎらう表現。
会議やイベント終了時の「お疲れ様でした」
仕事の会議やイベントが終わった後に言う「お疲れ様でした」は、参加への感謝と終了の合図という、2つの役割を持ちます。
例文と解説↓
- Thanks everyone for your time today.
→ 会議全体を労う丁寧なまとめ言葉。会議の取りまとめをするファシリテーターの立場から使うのも自然。 - That was a productive meeting.
→ 「有意義な会議でした」とポジティブに締めるフレーズ。 - Let’s call it a day.
→ 「今日はここまでにしよう」。打ち上げや作業後にも使えます。”call it a day”が「今日はここまで」という意味の慣用句です。
関連記事:英語会議のファシリテーターを任されるのはメリットしかない?理由と使える表現をご紹介!
関連記事:英語会議で使える司会進行フレーズ厳選15選!今日から使える必須フレーズまとめ
チャットやメールでの「お疲れ様でした」
英語圏では「お疲れ様でした」のような決まり文句はあまり使われませんが、感謝の気持ちや丁寧な締めくくりで代用します。
例文と解説↓
- Thank you again for your help.
→ 繰り返しの感謝を表す定番表現。メールの締めに使いやすい。 - I appreciate your time and support.
→ 手伝ってもらったり、時間を使ってくれたことに対する感謝の気持ちを伝えます。少しフォーマルな言い方で好印象。 - Looking forward to working with you again.
→日本語で言う「またよろしくお願いします」に相当する言い方です。丁寧かつ前向きな一文で「お疲れ様」のニュアンスを伝えられます。
関連記事:【ビジネス英語】明日からそのまま使える!英文メールフレーズ集
関連記事:ビジネス英文メール、レターが書きやすくなる!基本のビジネス英語フレーズ集!
「お疲れ様」は文化的に英語には存在しない?


冒頭でお伝えした通り、英語圏では、「相手の頑張りに対して決まり文句を言う」文化があまりありません。
日本では「お疲れ様」がコミュニケーションの潤滑油として機能しますが、英語ではその代わりに「具体的な感謝」や「ねぎらいの行動(コーヒーを奢るなど)」で気持ちを表す傾向があります。
つまり、「英語に訳す」のではなく、「英語文化に合わせてどう伝えるか」が大切だということですね。
「お疲れ様」を表す英語の使い方・ニュアンスの注意点


「お疲れ様」を英語で伝える時にも、使い方や伝え方にいくつか注意点があります。
- “Good job”は目上に使いづらい?
→ 一般に “Good job” は「よくやったね」みたいな感じで上から目線に聞こえることがあるため、上司や目上の人には “I appreciate your effort.” のように丁寧な表現が無難です。 - チャットでは略語にも注意
→ “Thx”や“TY”(どちらもThank youの意味)など、略しすぎるとカジュアルすぎる印象になるので、ビジネスシーンやまだ交流の薄い人の前では避けた方が無難でしょう。 - 表情と声のトーンも大事
→ 日本語では言葉だけで十分伝わることでも、英語ではトーンや表情での「ねぎらいの気持ち」を表現するのも大切だと言えます。
シチュエーションごとに、自分が伝えたいニュアンスを考えて適切に使うのが大切だというわけですね。
まとめ


この記事では、「お疲れ様」を意味する英語表現を例文付きでお伝えしました。
「お疲れ様」という言葉が、相手を労う日本語的な文化に根差しています。
なので、直接「お疲れ様」を意味する英語がないのは、最初は不便に感じるかもしれません。
しかし、この記事でお伝えしたフレーズを参考に、相手の立場や状況に寄り添った言葉選びを意識すれば、自然と相手を労う英語が口から出るようになっているでしょう。
この記事でお伝えしたことが、あなたの英語の表現力をより豊かにできれば幸いです。
また、英語学習方法にお悩みの方や英会話スクールで英語力が思っていたより伸びなかったという人におすすめなのが、英語コーチングです。
英語コーチングのTORAIZでは、あらゆる英語学習の中から、あなたにとってベストな英語学習をカスタムして、飛躍的な英語力の向上を図ることが出来ます。
英語コーチングとは、ただ英語を教えるだけでなく科学的根拠に基づいて効果的な勉強法を無理なく継続させる事に注力した英会話サービスです。
TORAIZは、そんなコーチング英会話の中でも継続率が91%以上!
英語力だけでなくコーチングの技術も洗練されたコンサルタントが、あなただけのために作られたスケジュールを管理しながら、無理なく挫折しない方法であなたをサポートします。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
短期で英語を話せるようになりたい方に
おすすめのスクールは「トライズ」
トライズは、日本人コンサルタントとネイティブコーチが専属でサポートしてくれる、英語コーチングスクール。レッスンは週3回確保される上に受け放題。マンツーマンの面談やメールで日々サポートも受けられて、他のスクールとは一線を画す本格的なプログラムになっています。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
受講生のインタビューもご紹介します。


トライズでの1年は、
一生につながる1年だったと思います。
プロキャディ杉澤伸章さん
インタビュー
Versant 29 → 40
目標:海外選手に英語でインタビューする。達 成
英語に関しては、1年前の僕と今の僕を比較すると、めちゃくちゃ成長しました。僕にとって情報源がものすごく増えたんです。 ゴルフ専門チャンネルで解説をしているのですが、そのときに現地の音声や解説者の声など英語でしゃべってくる音声が全て聞こえてきます。
それはテレビでは放送されていないのですが、映像だけでは入ってこない情報が耳から入ってくるので、それを聞きながらしゃべっています。 現地のリポーターや解説者は一番リアルな情報なので、それが耳に入ってくることによって、例えば解説でも「今、現地ではこういうことを言っていますね」ということが、スッと言えるようになりました。



















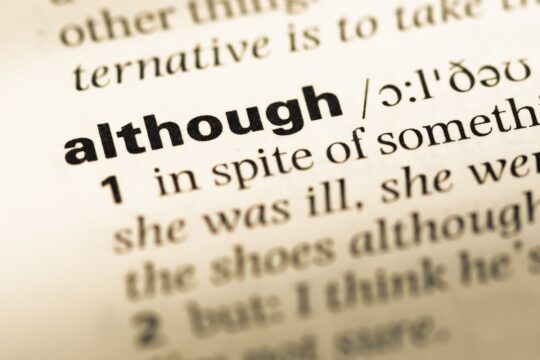



![TORAIZ[トライズ]](https://toraiz.jp/english-times/assets/img/banner/toraiz_main.png)