ESAT-Jとは?試験概要やサンプル問題、中学生がスピーキング力を身につけるコツについて解説
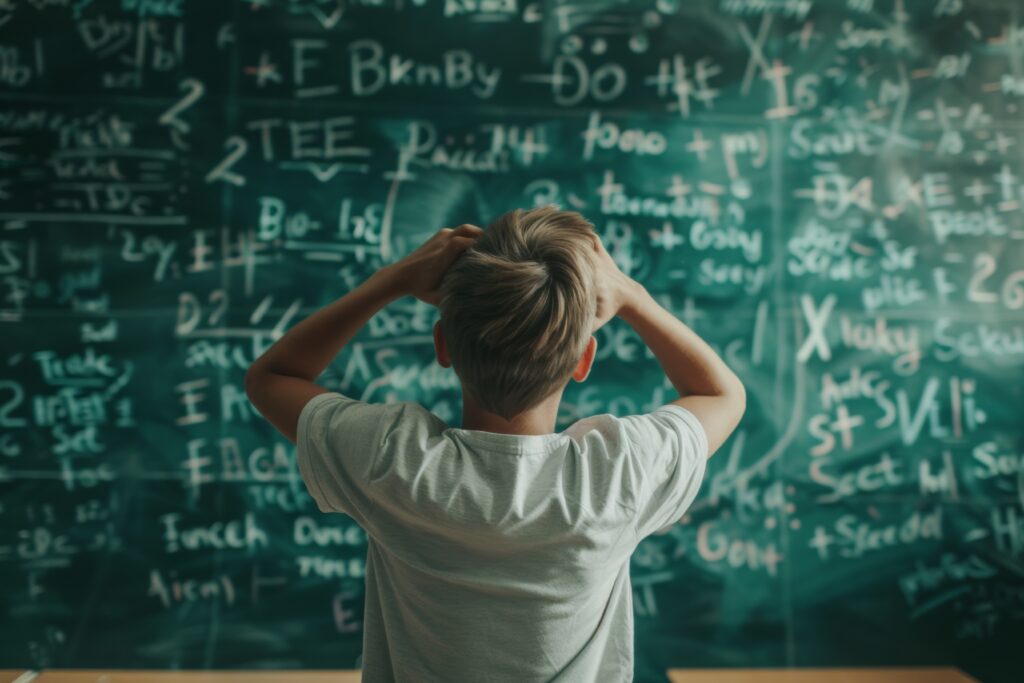
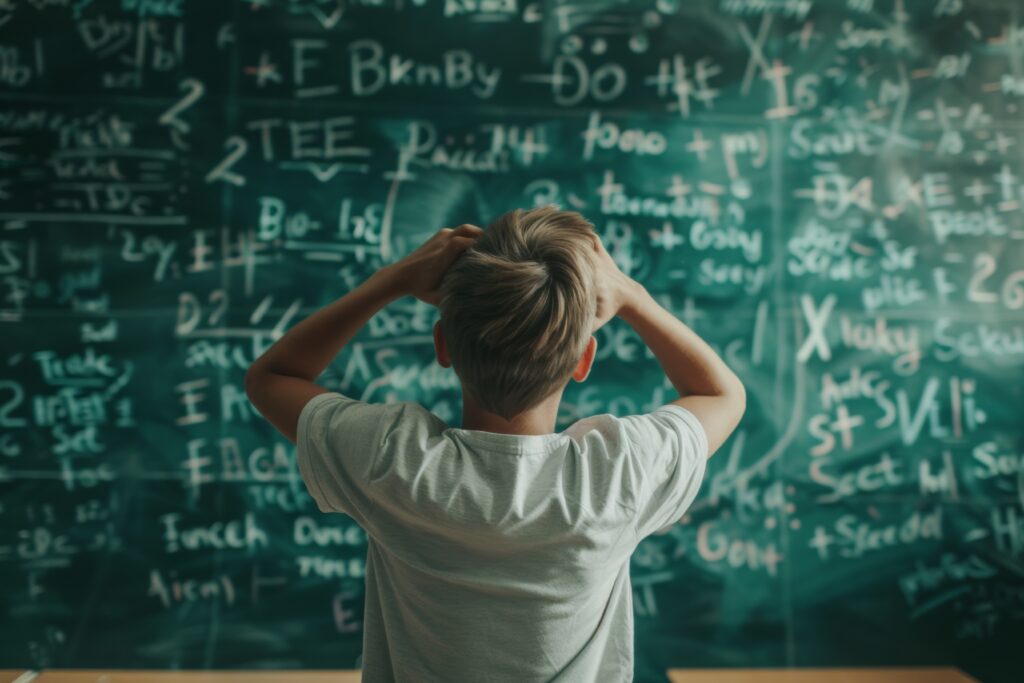
ESAT-J(中学校英語スピーキングテスト)は、東京都が実施する中学生向けの英語スピーキング能力を測る試験です。
このテストは、生徒が日常的な会話の中で自分の考えを英語で表現できるかを評価することを目的としています。
特に、スピーキング力を測ることに焦点を当てており、試験内容は会話形式で進行します。生徒は自分の意見や考えを英語で述べ、相手とのコミュニケーションを通じて、実際の英語力を試されます。
本記事では、ESAT-Jの試験概要や、その目的、重要性について解説し、試験を受けるためのポイントを紹介します。
中学生がどのようにスピーキング力を向上させ、ESAT-Jに臨むべきかを学ぶための参考になります。
目次
ESAT-Jとは?


ESAT-J(中学校英語スピーキングテスト)は、東京都教育委員会が実施する中学生向けの英語スピーキング能力を測る試験です。
目的は、生徒が実際のコミュニケーションにおいてどれほど英語を使えるかを評価することです。このテストでは、英語を使って自分の考えを表現する力や、他者と効果的にコミュニケーションを取る能力を重視しています。
試験内容は、日常的な会話の中で起こりうる場面を想定しており、生徒は指定されたトピックに対して意見を述べたり、質問に答える形式で進行します。
ESAT-Jは、英語教育の質の向上を目的としており、これからの英語学習における重要な一歩を踏み出すための大きな機会となります。
ESAT-Jの試験概要
ESAT-Jには、中学校の学年ごとに以下3つの種類があります。
- ESAT-J YEAR1
- ESAT-J YEAR2
- ESAT-J YEAR3
それぞれA〜Dの4つのパートで構成されています。出題形式と出題数は以下のとおりです。
ESAT-J YEAR1
| PART | 出題形式 | 出題数 |
| A | 英文を読み上げる | 1 |
| B | 質問を聞いて応答する/意図を伝える | 3 |
| C | イラストを英語で説明する | 1 |
| D | ストーリーを英語で話す(3コマ) | 1 |
ESAT-J YEAR2
| PART | 出題形式 | 出題数 |
| A | 英文を読み上げる | 2 |
| B | 質問を聞いて応答する/意図を伝える | 4 |
| C | イラストを英語で説明する | 1 |
| D | ストーリーを英語で話す(3コマ) | 1 |
ESAT-J YEAR3
| PART | 出題形式 | 出題数 |
| A | 英文を読み上げる | 2 |
| B | 質問を聞いて応答する/意図を伝える | 5 |
| C | ストーリーを英語で話す(4コマ) | 1 |
| D | 自分の意見を述べる | 1 |
どれも出題形式や出題数が似ていますが、わずかに異なります。
ESAT-Jのサンプル問題


ESAT-Jのサンプル問題は、以下よりご確認いただけます。
中学生が英語のスピーキング力を身につけるために大切なこと


中学生が英語のスピーキング力を身につけるために大切なことは以下の3つです。
- できるだけ早く「英会話は楽しい」という経験をさせる
- 使える単語を増やす
- 間違いを気にせずに話せる環境を与える
それぞれ詳しく見てみましょう。
できるだけ早く「英会話は楽しい」という経験をさせる
中学生が英語のスピーキング力を身につけるために最も大切なのは、「英会話は楽しい」と感じる体験を早期に提供することです。
英会話の初期段階では、どうしても学習が難しく感じられることが多いですが、楽しさを感じることで学習意欲が高まり、スピーキング力が自然に向上します。
英語を使うことがプレッシャーではなく、楽しいことだと感じるように促すことが重要です。また、英会話を実際のコミュニケーションの場で使用できると感じる機会を増やすことも効果的です。
例えば、英語を話すことが自分の意見を伝える手段となり、友達や先生との楽しい会話ができる場面を積極的に作ることが、スピーキング力の向上に大きく貢献します。
単語だけでも構わないので外国人と話してみて「通じた」という成功体験を得ることも大切です。
早い段階でこの経験を積むことが、英語学習を継続するためのモチベーションを高め、英語に対するポジティブな態度を育てる土台となります。
使える単語を増やす
英語のスピーキング力を向上させるためには、使える単語を増やすことが非常に重要です。
スピーキングは、自分の考えや意見を伝えるために言葉を使う能力が求められるため、語彙力を強化することがそのまま会話力の向上に繋がります。
しかし、単に単語を覚えるだけではなく、実際の会話で使える単語を中心に学ぶことがポイントです。例えば、日常生活でよく使われる表現や、学校や趣味に関連する単語を覚えると、英会話の中で積極的に使用できるようになります。
さらに、単語を覚えたら実際に使う場面を設けることが大切です。例えば、日常的に英語で話す練習をすることや、クラスでのディスカッションに参加することが、学んだ単語を実践的に使う機会を提供します。
使える単語を増やし、それを使いこなせるようになることで、自信を持ってスピーキングができるようになります。
中学英語さえ使いこなせるようになれば、基礎的な英会話はできるようになるとされています。
間違いを気にせずに話せる環境を与える
中学生が英語のスピーキング力を身につけるためには、間違いを気にせずに話せる環境を提供することが重要です。
多くの学習者が英語を話す際に、間違えることを恐れて話すことに躊躇しますが、間違いは成長の一部であると理解させることが、スピーキング力を高める鍵となります。間違いを恐れず、積極的に話すことで、語学力は飛躍的に向上します。
教師や保護者は、生徒が間違いをした際に優しく修正し、間違いを学びの一環と捉えることができる環境を作ることが大切です。
例えば、英語で自由に話す時間を設けることで、生徒は自分のペースで会話を進め、間違えながらも自信を持って話す経験を積むことができます。
また、他の生徒も同じように間違えることが許される環境が整っていると、恥ずかしさを感じることなく英語を話せるようになり、自然な会話ができるようになります。
保護者のスピーキング力向上にはTORAbitがおすすめ


TORAbit(トラビット)は、AIによる添削機能を活用しつつ、スマホ1つでシャドーイングや瞬間英作文を学べるAI英語学習アプリです。
シャドーイングや瞬間英作文は、スピーキング力を向上させる上で欠かせない勉強法です。
TORAbitのシャドーイングでは、音声を録音してAIに添削してもらいます。音読などステップに分けてシャドーイングを実践するので「シャドーイングが難しい」と感じている人にもおすすめです。
また瞬間英作文では、さまざまな場面で使用する英語表現を学べます。
TORAbitは7日間無料で利用できます。興味がある方はぜひチェックしてみてください。
関連記事:TORAbit(トラビット)とは?サービスの特徴や使い方、使用してみた感想を紹介
まとめ
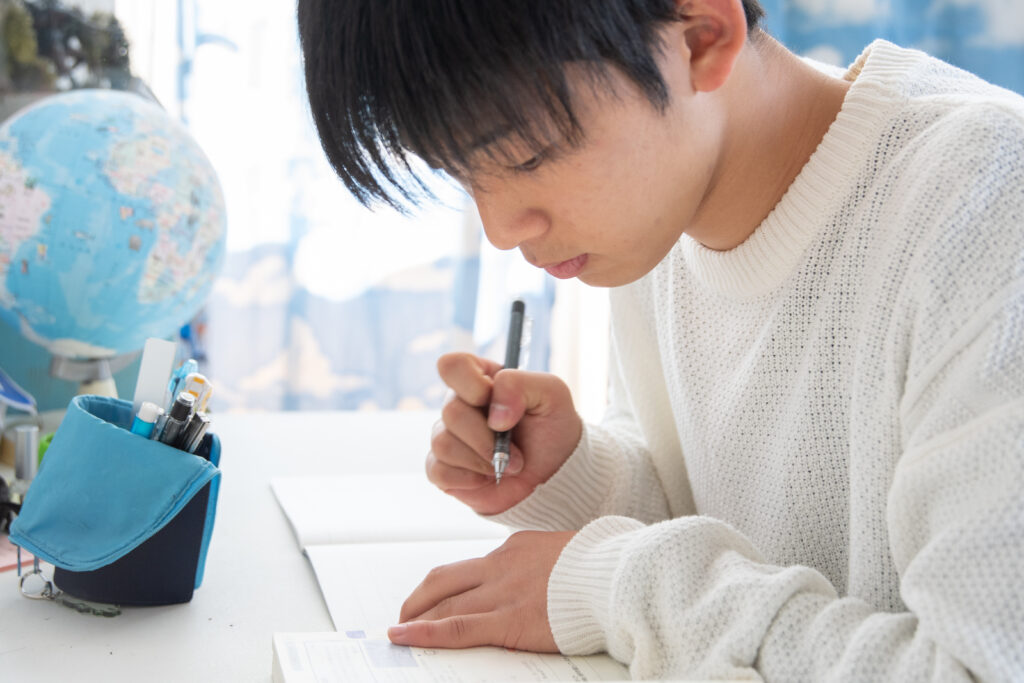
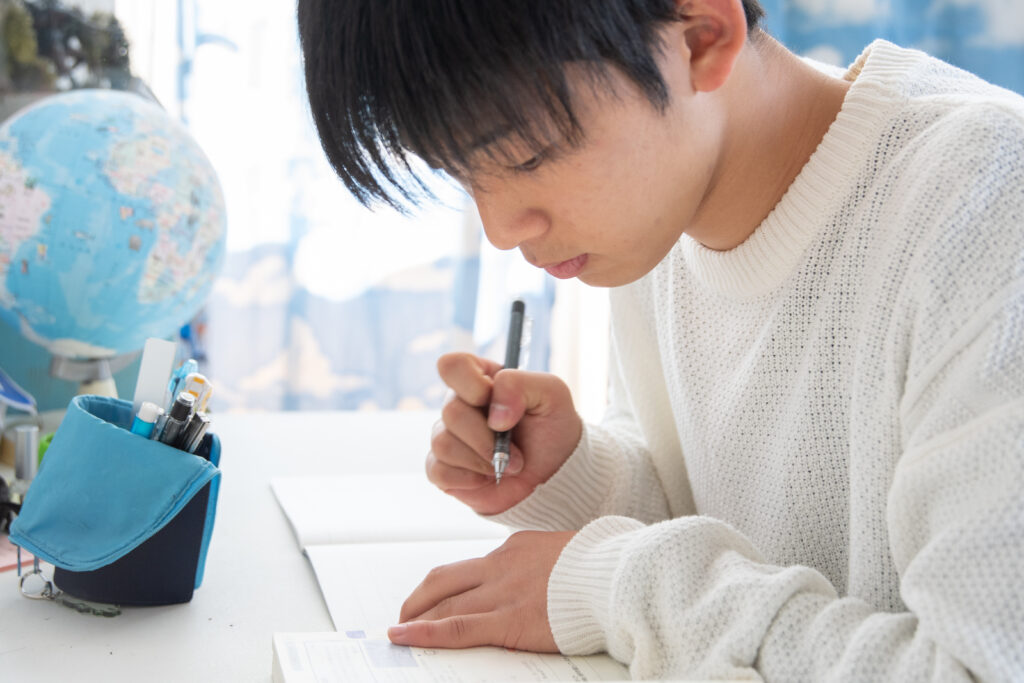
ESAT-Jは、中学生の英語スピーキング能力を評価する重要な試験であり、英語を使って実際のコミュニケーション能力を試す場です。
試験では、日常的な会話や自分の意見を英語で表現する能力が求められ、リスニングとスピーキングの力がバランスよく評価されます。
生徒がこの試験を受けるためには、早期に「英会話は楽しい」と感じる経験を積むこと、使える語彙を増やすこと、そして間違いを恐れずに積極的に英語を使うことが大切です。
ESAT-Jは、英語教育をより実践的なものにするための一歩となり、生徒たちに自信を持って英語を使う力を育んでいます。
短期で英語を話せるようになりたい方に
おすすめのスクールは「トライズ」
トライズは、日本人コンサルタントとネイティブコーチが専属でサポートしてくれる、英語コーチングスクール。レッスンは週3回確保される上に受け放題。マンツーマンの面談やメールで日々サポートも受けられて、他のスクールとは一線を画す本格的なプログラムになっています。
「短期間でどうしても英語が話せるようになりたい」という方には、おすすめのスクールです。
受講生のインタビューもご紹介します。


トライズでの1年は、
一生につながる1年だったと思います。
プロキャディ杉澤伸章さん
インタビュー
Versant 29 → 40
目標:海外選手に英語でインタビューする。達 成
英語に関しては、1年前の僕と今の僕を比較すると、めちゃくちゃ成長しました。僕にとって情報源がものすごく増えたんです。 ゴルフ専門チャンネルで解説をしているのですが、そのときに現地の音声や解説者の声など英語でしゃべってくる音声が全て聞こえてきます。
それはテレビでは放送されていないのですが、映像だけでは入ってこない情報が耳から入ってくるので、それを聞きながらしゃべっています。 現地のリポーターや解説者は一番リアルな情報なので、それが耳に入ってくることによって、例えば解説でも「今、現地ではこういうことを言っていますね」ということが、スッと言えるようになりました。


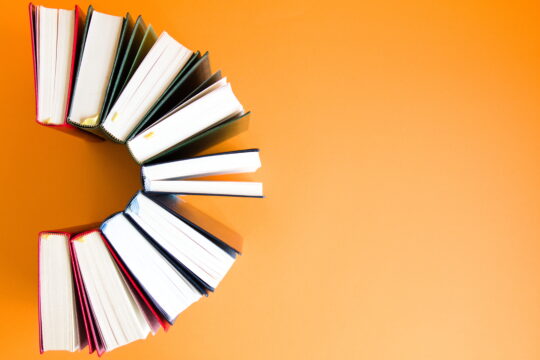
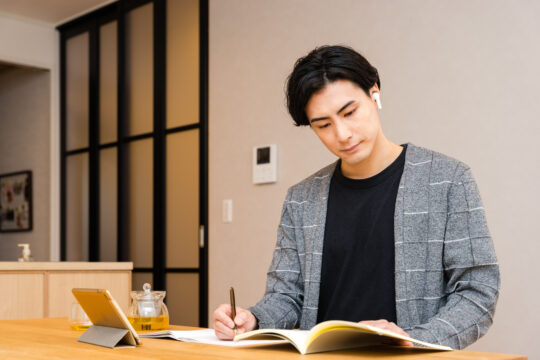
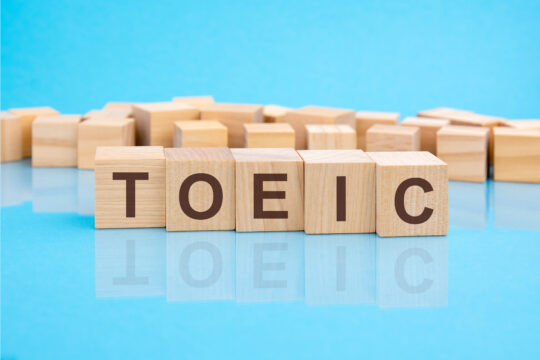




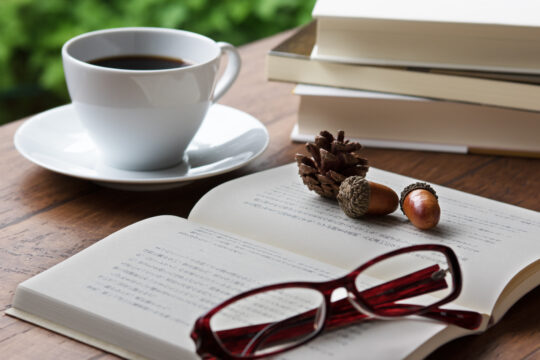













![TORAIZ[トライズ]](https://toraiz.jp/english-times/assets/img/banner/toraiz_main.png)