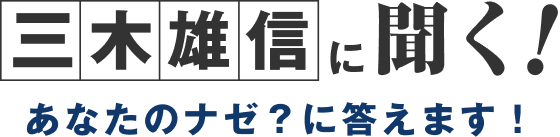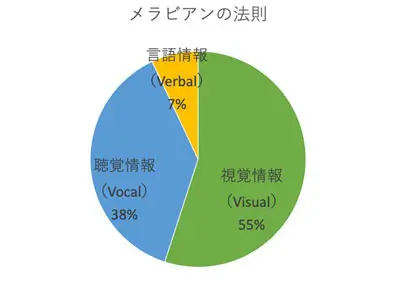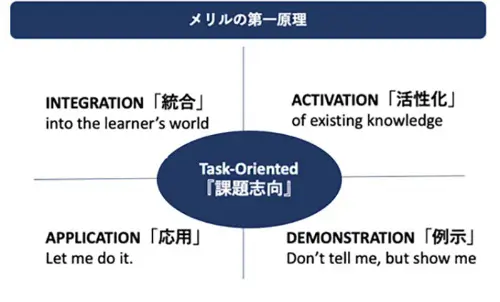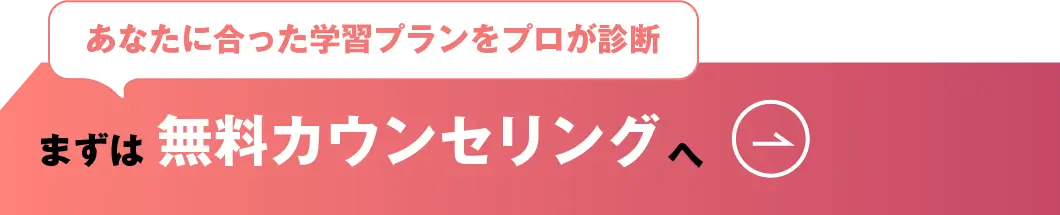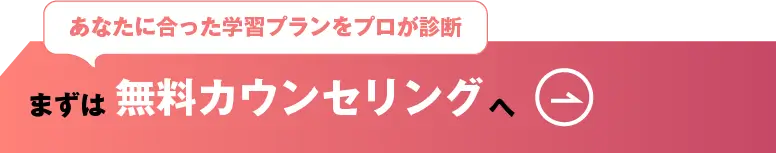Q.031
毎年「今年こそ英語を」と思うのに、達成できません
毎年、年初に今年こそ英語をマスターしようと思って学習を開始しますが、どうしても達成できません。どうしたら今年こそマスターできるでしょうか。
A.
結論:10年計画→年間目標→必要時間の算出→教材確保→本計画作成、この順序が成功のカギです
いきなり1年の計画を立てるから失敗します。
まず10年先のゴールを決め、そこから逆算して今年の目標を設定し、必要時間を明確にして計画を立てれば、今年こそ達成できます。
ほとんどのビジネスパーソンが同じ経験をしています。今年こそ英語をマスターしましょう。
いきなり1年計画はNG:まず10年計画を立てる
1年の計画を立てる前に大事なことがあります。まず10年ごとの人生計画を立てることです。
これはソフトバンクグループの孫正義会長から学んだことです。孫氏は19歳の時に人生の50年計画を立てました。これがソフトバンクと孫氏の成功の第一歩でした。
孫正義氏の50年計画:
・20代で業界に名乗りを上げる
・30代で軍資金をためる
・40代で一勝負して、大きな事業に打って出る
・50代でそれをある程度完成させる
・60代で次の経営陣にバトンタッチし、300年以上続く企業に仕上げる
20代から50代までの計画は全て達成しています。20代でソフトバンクを創業し、30代で株式公開、40代で通信事業参入、50代でiPhone独占販売で通信事業の地歩を固めました。現在は10兆円ファンドで計画を仕上げようとしています。
大事なのは、1年の計画を立てる前にさらに大きな方向感が必要ということです。
実例:10年計画で海外赴任を実現したNさん
IT企業で働くNさん(20代)は「30代で海外勤務しながら子育てをしたい」という10年計画を立てました。そのためのステップを的確に踏んでいます。
Nさんの実行ステップ:
1.20代半ばまで:自分の仕事で成果を上げることに集中
2.20代後半:ためた資金で国内大学のMBAを取得、結婚
3.その後:TOEIC L&Rスコアを取得し、海外担当部門に異動
4.現在:話すための英語を特訓中
5.来年度:海外赴任予定
人生計画をしっかり立てて非常にうまくいっている例です。
50年分は難しくても、10年先のゴールを決めておくことは非常に重要です。うまくステップを踏むために必要不可欠なのです。
年間計画の立て方:5つのステップ
10年計画に基づき、今年のゴールを具体的に設定し、1年の計画を立てます。重要なことは、そのゴールに到達するまでにかかる時間を明確にすることです。
ステップ①:ゴールと必要時間を把握する
ゴールに到達するまでに必要な時間は、様々な物事である程度決まっています。
例:ゴルフで120切り
・コースに出られるまで:3カ月程度
・120を切る:週1回の練習で1年が標準
例:資格取得
・公認会計士試験合格:3000時間
・宅地建物取引士試験合格:300時間程度
例:英語習得
・大学卒業後、ビジネスで使えるレベル:1000時間
資格スクールや語学スクールのサイトにある「短期間で合格・習得」事例は、まれなケースの可能性がありますので、気を付ける必要があります。
高校時代にインターハイ出場、大学入試模試の偏差値70超といった人でない限り、標準的な計画を立てるのが基本です。
ステップ②:1週間の学習時間を算出する
自分が学習のために投じられる時間を1週間単位で算出します。
例:
・平日毎日1時間+土日各5時間=週15時間
・宅建士(300時間必要)なら20週=約6カ月前から準備
これで仮計画としましょう。
ステップ③:教材一式をそろえる
ゴールまでの教材一式をそろえます(オンラインやスマホアプリでも可)。それぞれの教材について、どのくらい学習時間が必要かをざっくり見積もります。
数日間その教材を使って実際に学習してみましょう。自分が1日でこなせるだいたいの量が分かってきます。
ステップ④:本計画を作成する
仮計画が達成できるか確認します:
・時間が足りない→1週間の学習時間を増やす工夫が必要
・時間が余る→模試や練習問題を追加(より確実に達成)
教材ごとにかかる時間を割り出し、取り組む順番に並べて予定通りに終わるか確認します。このステップを踏んで本計画を作りましょう。
ステップ⑤:リアルタイムに見直す
計画をリアルタイムに見直しながら進めます。
・進捗が遅い場合:1週間の中で調整
・それでも追いつかない:教材を減らしたり計画自体を見直す
大事なことは、全体の計画を常に把握しておくことです。
成功する年間計画の全体像
1.10年先のゴールを決める 大きな方向感を持つ
2.今年のゴールを具体的に設定 10年計画から逆算
3.ゴール到達の必要時間を把握 標準的な時間で仮計画
4.1週間の学習時間を算出 現実的な時間配分
5.教材一式をそろえて試し学習 実際にかかる時間を測定
6.本計画を作成 教材ごとの時間と順番を明確化
7.リアルタイムに見直し 全体計画を把握しながら調整
まとめ:計画の質が成果を決める
多くの人が「今年こそ英語を」と思いながら達成できないのは、いきなり1年の計画を立てるからです。
成功のカギ:
・10年先のゴールから逆算する
・必要時間を現実的に見積もる
・試し学習で自分のペースを把握する
・全体計画を常に把握する
以上のことに注意して計画を立ててください。今年こそきっとしっかりした成果が上がります。応援しています。