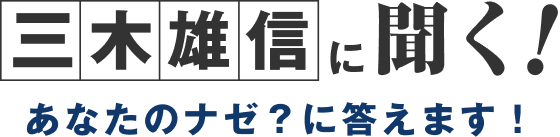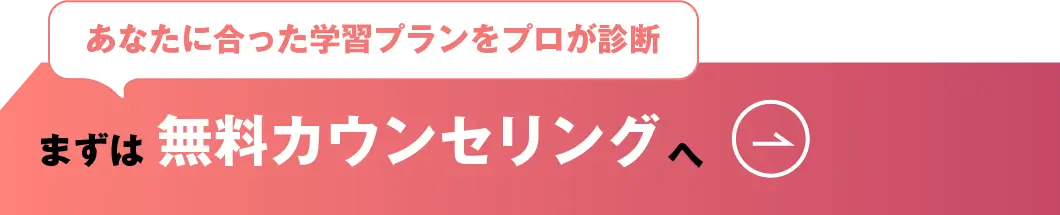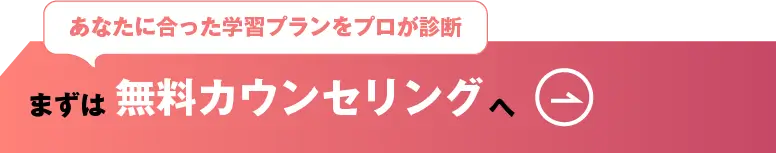Q.081
生成AIが発達しても英語学習は必要でしょうか?
ChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、コンタクトレンズ型ディスプレーや脳内イメージの可視化技術も開発されています。こうした技術が実用化されれば、もはや英語を学ぶ必要がないのではないでしょうか。英語学習を続けるべきか迷っています。
A.
結論:買い物や旅行での簡単な会話は不要になりますが、ビジネスや学問での英語習得の必要性は逆に高まります。イノベーションには対面コミュニケーションが不可欠で、リアルタイムで進む議論についていくには英会話力が必須です。抽象的な概念を伝えるには言語そのものが必要だからです。
日常会話は翻訳機で十分になる
「買い物や旅行での簡単な会話は学習不要になる」という点は、ほぼ確実でしょう。現在でも携帯型翻訳機を使えば、日常的な会話は十分に翻訳できます。今後は同等以上の機能がスマートフォンで使えるようになるはずです。
テクノロジー機器の普及パターンを見れば明らかです。1980年代、日本では「書院」などのワープロ専用機が使われていました。しかしパソコンの普及とワープロソフトの性能向上により、専用機は姿を消しました。
同じように、携帯型翻訳機ではなく誰もが持つスマホで世界中の人とコミュニケーションする時代が近づいています。実際、AIを内蔵し通話内容をリアルタイムで音声翻訳するスマホが既に発表されています。
ビジネスでは対面コミュニケーションが重要
一方で、ビジネスや学問の研究に使う英語習得は今後も必要です。確かに文章翻訳もAIの発達で飛躍的に向上しています。Google Scholarで海外の論文を見つけ、DeepL Proで日本語に翻訳することも可能です。
しかし英語をマスターすることが不要になるとは考えていません。イノベーティブな仕事や研究には、対面でのコミュニケーションが重要だからです。
その証拠に、コロナ禍が明けた現在、米国のビッグテック——Alphabet(グーグルの親会社)、Amazon、Meta、Appleをはじめ、出社を要請するIT企業が増えています。
本来、IT企業のエンジニアなら在宅勤務でも高い生産性を上げられるはずです。それでも各社が出社を求めている事実が、対面の重要性を物語っています。
リアルタイムの議論に翻訳は追いつかない
イノベーティブな仕事では、英語が話せるメンバーの中でスマホの翻訳アプリを見ながら会話するのは現実的ではありません。周りが流暢な英語で議論を進める中、1人だけ翻訳結果を確認してから発言しようとしても、会話のスピードについていけず発言の機会を失ってしまうでしょう。
今後、人間の脳内イメージを映像化する技術が開発されても、状況は変わりません。「すしが食べたい」という具体的な欲求なら、すしやすし屋のイメージを表示してコミュニケーションが成立するでしょう。
しかし抽象的な概念を映像で伝えるのは困難です。なぜなら英語話者は英語で、日本語話者は日本語で抽象的な概念を考えているからです。したがって抽象概念のコミュニケーションでは、言語を英語か日本語のどちらかに統一する必要があります。
まとめ:
口頭による英語のコミュニケーション力は、テクノロジーが進化してもますます必要になります。むしろ、グローバルなビジネス環境で活躍したいなら、その重要性は高まる一方です。ぜひ英語学習に積極的に取り組んでみてください。応援しています。