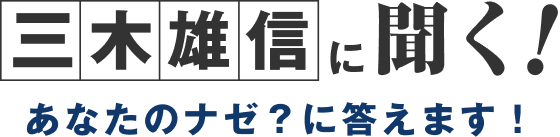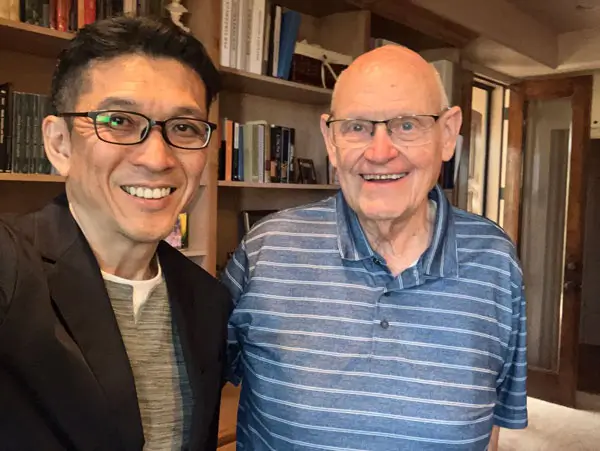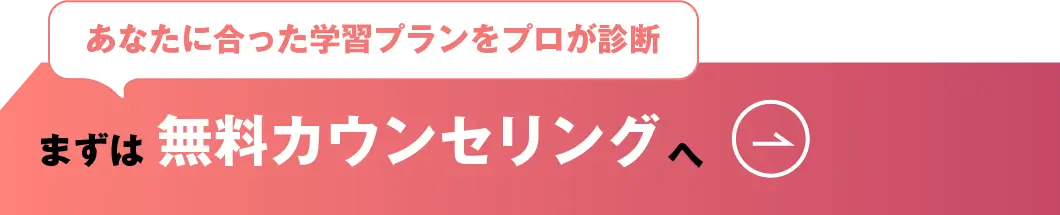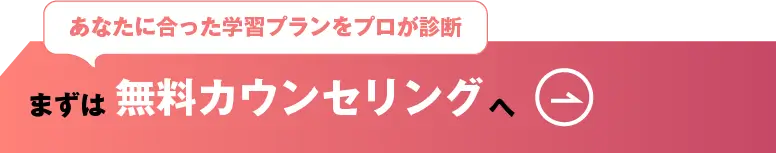Q.091
米国人にまくしたてられてしまい会話が成立しませんでした。どう対処すべきでしょうか?
日本人とコミュニケーションを取ったことがなさそうな米国人とオンライン会議をしたとき、相手からまくしたてられてしまい会話が成り立ちませんでした。オンラインや電話で会議をする際に、英語でうまくコミュニケーションするための交渉術やマインドセットを知りたいです。
A.
結論:最も大事なのは「分からない」とはっきり伝えることです。これは「方略的能力」というコミュニケーション言語能力の一つです。ポイントは2つ。確認する能力を磨くこと、そして事前準備を徹底すること。想定質問と回答のメモを用意し、チャット機能で質問を受け付ける、Zoomの文字起こし機能を活用するなど、テクノロジーも味方につけましょう。英語力ではなくコミュニケーション能力で勝負するマインドセットが鍵です。
オンライン会議が生んだ新しい課題
オンライン会議の普及で、思わぬ壁に直面する人が増えています。
以前なら海を越えての打ち合わせには相応の準備が必要でしたが、今やワンクリックで世界中と繋がれます。その結果、日本のビジネス文化を全く知らない相手と、いきなり対峙する場面が増えたのです。
黙り込むのが最悪の選択
こうした状況でどう対応すべきか。
答えは明確です。「理解できていません(Could you repeat that?)」とストレートに伝えることです。
ところが多くの日本人は恥ずかしさから、このシンプルな一言が言えません。結果、黙り込んでしまう。実はこれが最悪の選択なのです。
「聞き返し」は立派なスキル
第二言語習得論では、「聞き返し」をコミュニケーション言語能力の1つと定義しています。このように言語能力だけでなく他の能力を使いこなしてコミュニケーションする能力を「方略的能力」と呼んでいます。

方略的能力はコミュニケーション言語能力を高めるために必要な能力の1つです。
方略的能力を高める2つのコツ
1. 要約して確認する
相手の話をおおよそ掴めているが、100%ではない——そんなとき使える技術です。
例えば製品の納期について議論している場面。「つまり、今月中に原料を調達できれば間に合う、という理解で合っていますか?」などと確認を入れます。
これで話の流れを整理しつつ、自分の理解をすり合わせられます。聞き流して誤解したまま進むより、遥かに建設的です。
2. 事前に準備を徹底する
オンライン会議は試験ではありません。カンニングペーパーを堂々と使えます。
プレゼンする側なら、想定質問と模範回答を英語で準備しておきましょう。手元にメモがあるだけで精神的な余裕が生まれ、相手の話を冷静に聞くことに集中できます。
さらにZoomのチャット機能を活用する手もあります。「質問はチャットでお願いします」と宣言すれば、リスニングのプレッシャーが一気に減ります。テキストなら知らない単語も調べられますし、落ち着いて回答を練れます。
プレゼンテーションを聞く側の立場でも同じです。事前に質問リストを英語で作っておき、積極的に話の流れをリードする。そうすれば言っていることが分からず黙ったままでいる状態を回避し、会議をコントロールすることができます。
テクノロジーをフル活用する
ビジネスのゴールは「流暢に話すこと」ではありません。「成果を出すこと」です。
そう割り切れば、使える武器は全て使うべきです。
Zoomにはリアルタイム文字起こし機能があります。「Otter」のような専用アプリと併用すれば、音声を可視化できます。聞き逃しても、テキストで確認できる安心感は大きいでしょう。
プレゼンを聞きながら質問を英文にまとめ、終了後にチャットで一気に送る——この作戦も有効です。事前準備の質問を使い回してもいいのです。プレゼン中に答えが出た項目だけ削除すればよいのです。
自動翻訳字幕は要注意
Zoomには会話を自動翻訳して字幕表示する機能もあります。ただしこれは慎重に。
英語がほとんど分からないレベルなら助けになりますが、ある程度話せる人が使うと、かえって混乱を招く恐れがあります。
実際に試してみると、英語と日本語の思考が入り混じって混乱することがあります。また、耳から入る音声情報と目から入る文字情報を同時に処理する必要があるため、非常に負荷がかかります。実は、2つの言語をリアルタイムで翻訳するには、単なる語学力以上の「2言語同時運用能力」が求められます。英語力が高い人であっても、同時通訳を行うのは難しく、同時通訳者は特別な訓練を積んでいます。
マインドセットを変える
まずは「英語力の高さではなく、コミュニケーション能力で勝負する」というマインドセットに切り替えましょう。しっかり準備を整え、テクノロジーを賢く活用すればうまくいくでしょう。応援しています。